



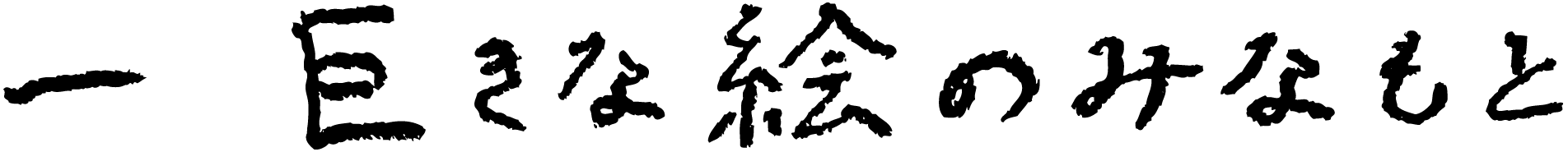
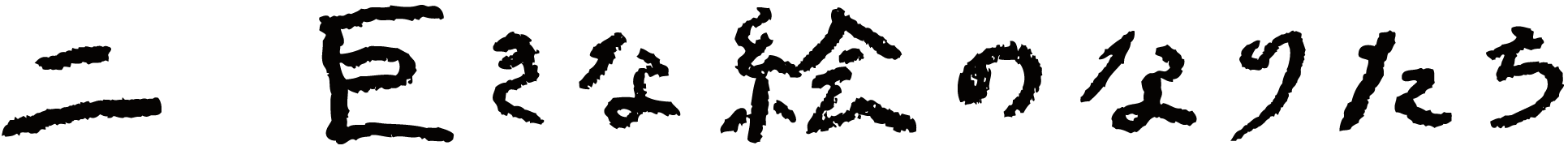
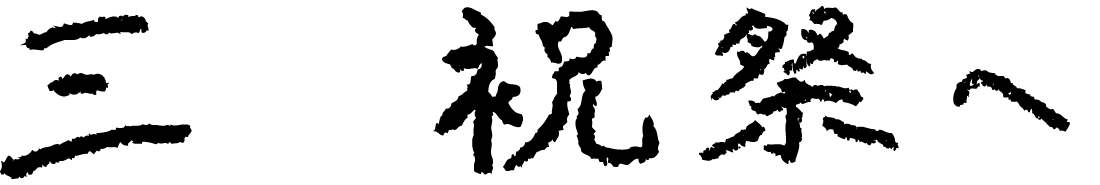
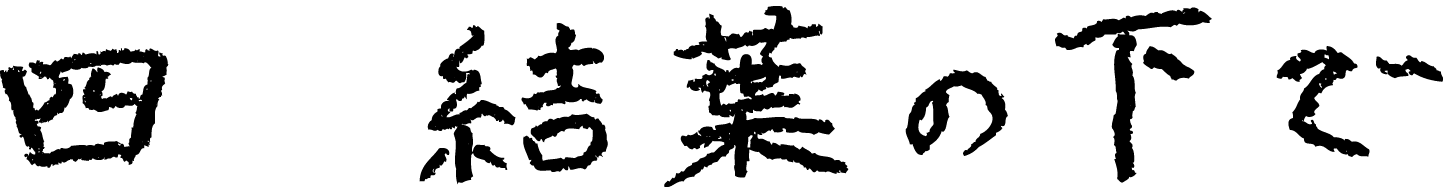
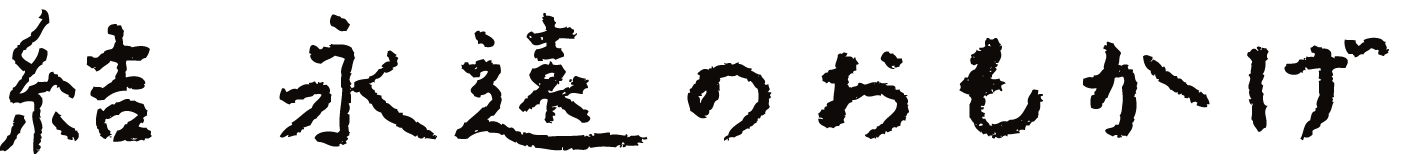
はじまりの灯 目次
序 去来する光
一 巨きな絵のみなもと
二 巨きな絵のなりたち
三 祝祭へ
2018年秋からはじまった巨きな絵の制作と展示、そのための舞台となったのは絵描きとして活動するなかで当時最もお世話になっていた場所の一つ、浜松市鴨江アートセンター(旧鴨江別館)だった。
かつて昭和初期に建てられた警察署庁舎を、市民の文化芸術活動の拠点として一般開放しているこの建物は、いつ訪れても居心地のよさを感じさせてくれる、光のきれいなところだった。まだ大学生だった頃から展示を何度かさせていただいたご縁もあって、東京から静岡に戻ってきてからもよく顔を出すようになり、自分にとってはひとつのホームのような場所となっていた。

鴨江アートセンターではアーティストを支援する事業「アーティスト・イン・レジデンス」が毎年行われており、審査に応募して採用されると、制作場所として館内の一室を数ヶ月にわたり無償提供され、期間中に制作物の成果発表を行えることになっていた。巨きな絵の制作を行うならこの場所をおいて他にない、そう考えていた自分は迷わずこの企画に応募した。その結果5月には無事に採用されることになり、11月から翌年の2月下旬までの約三ヶ月半、館内でアトリエ制作を行うことが決まった。
こうして絵描きとして3年(大学生の頃も含めると7年)お世話になった浜松という場所で、自分なりの気持ちを返すうえでもこのうえない環境の中で、巨きな絵と向き合う日々は始まりをむかえることとなった。
レジデンスの成果発表となる個展は、2019年2月下旬に開催することになった。スケジュールがきまったのは2018年夏のことで、秋までに巨きな絵の準備を進めておきたかったものの、仕事や他の制作に思いのほか追われてしまい、結局漠然とした構想段階からほとんど進展がないまま秋をむかえた。
けれどこれまでにすでに見てきた、大切な作品たちによる影響の多くが自分の中に根づいていったのは、まさにこの時期でもあった。
 約3ヶ月間のあいだ、巨きな絵の制作を行ったアトリエ
約3ヶ月間のあいだ、巨きな絵の制作を行ったアトリエ2018年11月1日、レジデンス初日。
鴨江アートセンターで部屋を借りての制作がいよいよはじまると、まずは巨きな絵のメインとなる部分として構想していた<四つの神話的場面>を描くための準備をはじめた。高さ約1.4m・幅約1.8mの絵を四枚繋ぎ合わせることによって、生命の曼荼羅のごとく巨大な一枚の絵として結ばれるこの場面は、無数の動植物がコラージュされることによって、その全体をなすものだった。
四枚の絵の中で主たるモチーフとしていち早く描くことが決まっていたのは、巨きな絵の制作からおよそ3年前に出会った、「木の鹿」や「枯葉の鳥」たちの存在だった。彼らをはじめとする、それまで連綿と続いてきた様々なイメージとの出会いを「絵を巡る変容の旅」としてひとつの物語に見立てたとき、それは創造の霊源そのものとなって、モチーフを次から次へと浮かびあがらせていった。さらに前章でみてきた「宮沢賢治の四象限」とも照応させてゆくことで、<四つの神話的場面>はその全体像が徐々に形づくられていくこととなる。
 <四つの神話的場面>のためのスケッチコラージュ
<四つの神話的場面>のためのスケッチコラージュ実際の描画に入る前に、まだ半分ほどしか決まっていなかったモチーフの配置をもう少しかためる必要があった。アトリエの壁に四枚の画用紙を貼り、それを<四つの神話的場面>の実際の構成図に見立てると、巨きな絵にまつわるモチーフを元にした種々のスケッチたちを次々とコラージュしていった。
ラフにモチーフを描いた小さなカードの絵、スケッチブックに描きためてきた巨きな絵にまつわる構想メモのほか、巨きな絵とは直接関係ない過去のスケッチから気に入っていたものたちも時折まぜていった。それらは絵を描くうえで発想の起爆剤となるような内容を多分に含んでいて、巨きな絵の創造をうながしていくうえで非常に大きなたすけとなるものだった。
 スケッチコラージュの細部
スケッチコラージュの細部スケッチは作品をつくるための準備や下書きという域をこえて、それ自体が完成されたひとつのいとなみであるように思う。幼い頃、落書きに夢中になっていた感覚と地続きの何かがそこにはあって、絵を描くこと、そして想像することのよろこびへといつでも立ち帰ることのできる原点として、スケッチはいつも制作の傍らにあった。
 アトリエの壁に貼っていたスケッチたち
アトリエの壁に貼っていたスケッチたち スケッチの一部
スケッチの一部少しずつ全体の構成がまとまっていくのにともない、巨きな絵を描画するための素材を準備する作業も並行して進めていった。これまでの作品制作においてはあくまでイメージの探求を重視し、画材はなるべく安価なもので済ませてきたものの、今回は少なくとも紙だけでもこだわってみようと考えていた。
様々な素材の紙を探すなか、東京・青山にあるグランピエという民芸品店が取り扱っていたネパールの職人たちによる手漉きの紙を発見する。三椏(みつまた)という、日本のお札にも使われる原料で漉かれたその紙は、ところどころに太い繊維が残る独自の豊かな風合いをもち、しわや破けといったものでさえも味わい深いものとして感じられた。
この手漉き紙を絵に使うために試行錯誤をかさねた結果、滲み止めとしてドーサ(膠液にミョウバンを混ぜたもの)を塗布した後、アクリル絵具を塗り重ねていくことによって、そのままコラージュ用の素材としてあつかえる「色紙」に加工できることがわかった。この色紙の存在が、巨きな絵を制作するうえでとても重要な素材となった。
 山の化身 / 2018
山の化身 / 2018巨きな絵をつくるためには、二百枚以上にもおよぶ膨大な数のネパール手漉紙を用意し、そのすべてを色紙に加工する必要があった。色紙にする工程自体は単純なものの、限られたスペースでの作業となるうえに乾き待ちの時間も含めると、一枚仕上げるだけでも半日以上は必要だった。さらにその色を決める作業も全体像を意識しつつ慎重に行う必要があったため、序盤のアトリエ制作の大部分は色紙の制作に費やすこととなった。
 ドーサ液をひいたネパール手漉紙
ドーサ液をひいたネパール手漉紙 仕上がった色紙たち
仕上がった色紙たち必要と思われる色紙をひととおり準備し終えた頃には、すでに制作開始から1ヶ月半をすぎていた。この時点で制作可能な時間のおよそ3分の1は過ぎていたことになる。
<四つの神話的場面>の描くべきモチーフはこの段階で大部分が見えてきていたものの、手付かずの部分も少なからず残っていた。しかしこれ以上頭のなかで考えるよりも、実際に手を動かすことで見えてくるものがあると判断し、ようやく本格的な描画やコラージュのための作業がはじまることになった。
 巨きな絵のコラージュ、最初の段階
巨きな絵のコラージュ、最初の段階まずは全体の図と地の関係や配色のバランス等をみるために、四つの場面とモチーフのかたちを意識しつつ色紙をちぎって床に蒔(ま)いていく。面積の関係上、アトリエの床は紙でほとんど埋めつくされてしまった。ここから先は絵の上を畑のように踏みしめながら、ひたすら種々のモチーフと対話し、発展させてゆく日々が続くこととなった。
 微妙な色味・質感の違いがイメージの振幅をさそう
微妙な色味・質感の違いがイメージの振幅をさそう 主たるモチーフのひとつ「木の鹿」のかたちを起こすところ
主たるモチーフのひとつ「木の鹿」のかたちを起こすところ全体の感じをおおまかに掴むと、今度は描くことの見通しが立ったモチーフから少しずつ描写し、かたちに起こしていった。ここからは木を見て森を見る、の果てしない繰り返しが続くことになる。
 夜空を埋め尽くす藍色の紙たち
夜空を埋め尽くす藍色の紙たち 主たるモチーフのひとつ「赤い鳳」と「枯葉の鳥」
主たるモチーフのひとつ「赤い鳳」と「枯葉の鳥」自分の背丈をゆうに超えるほどの巨大な絵をコラージュしていく過程は、まるで絵の時空間に自らが取り込まれていくかのようだった。手先だけでなく、身体全体で絵の中を行き来していると、天地がひっくり返ったかのような錯覚が幾度も生じて、目がくらんだ。
 「赤い鳳」と「木の鹿」がおおむね仕上がったところ
「赤い鳳」と「木の鹿」がおおむね仕上がったところ 1月下旬、朝陽に照らされた絵
1月下旬、朝陽に照らされた絵2月をむかえる頃、ようやく四枚の場面すべてにモチーフが根を下ろし、その時点で想定していた描写のうちの7割程度を仕上げることができた。けれど<四つの神話的場面>は、あくまでも絵全体の面積の総和としてみるならば、未だその半分程度にすぎなかった。