



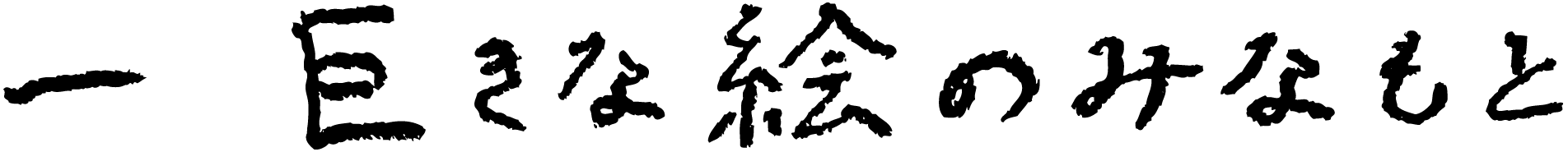
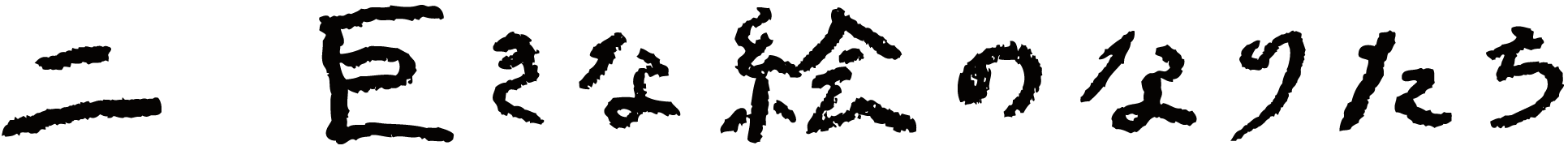
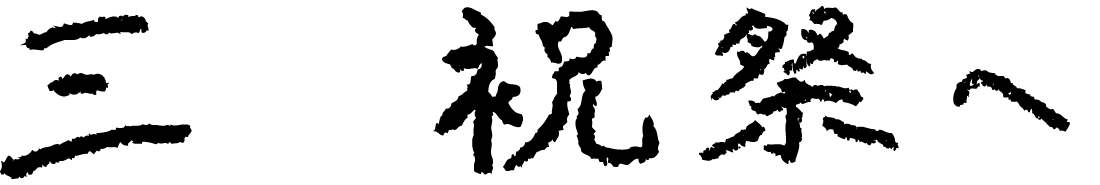
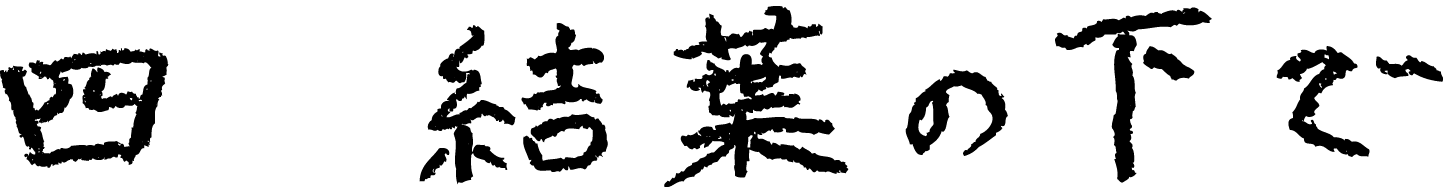
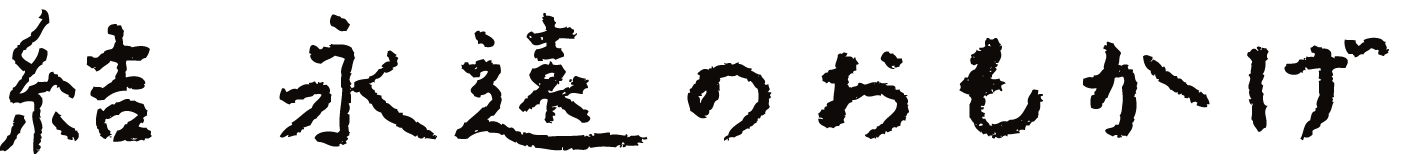
はじまりの灯 目次
序 去来する光
一 巨きな絵のみなもと
二 巨きな絵のなりたち
三 祝祭へ

美がまえにある
美がうしろにある
美が上を舞う
美が下を舞う
私はそれにかこまれている
私はそれにひたされている
若い日の私はそれを知る
そして老いた日に
静かに私は歩くだろう
このうつくしい道のゆくまま(真木悠介「気流の鳴る音」より ナヴァホ族の讃歌)
巨きな絵と旅をした日々から、気がつけばもう三年半が過ぎていた。
闇のなかで光を追い求め続けたかのような二十代後半はいつのまにか過ぎ去り、当たり前のように三十代を迎え、その後何事もなく生きているという事実が、時々ふとたまらなく不思議に思えてくる。
いま自分は北海道の一軒家で、大切な人と一緒にふたりで暮らしている。そしてまた絵を描く日々のただなかへと、ふたたび舞い戻ろうとしている。
先月、ふたりで話をして決めたことがある。来年から巨きな絵を再び各地で展示しようということ、そしてその最後には、巨きな絵を燃やそうということを。
✳︎
一体どうやってここまで来たというのだろう。忘れようにも忘れられないことが、あまりにも多く過ぎ去った三年半だった。
出会いと別れとが波のように寄せてはくりかえしたこと、その時々の喩えようのないまぶしさが現在へと反照されるたび、絵にも詩にもならない がこぼれて、世界は揺籃する。

巨きな絵を描いてからしばらく経ったある秋の日に、ある母娘と海で出会った。
インターネットをとおしていつからか知り会い、いつか母子像を描いていただけたら、そう伝えていただいたことが直接お会いするきっかけとなった。いつだったか、自分の誕生日である5月1日がすずらんの日を意味することを、母親であり自分とそう年齢の変わらないであろうその人は教えてくれた。
海でほんの束の間一緒に過ごすあいだに、一体何が起こったのか、今でも自分にはよくわからない。けれどふたりと別れたあとで、自分はもうすでに闇をぬけて光の中にいるのだということ、光は自分の中にも内在しているのだということ、それらを伝えてくれたのが先のふたりであったことを知り、どうしようもなく目頭が熱くなった。
この世に降り立ってから初めて受けとったかのようなそれは、"たましい"という他に言いようのないものだった。帰りの車を走らせながら、シートに残っていた海の砂粒たちが散乱する粒子のようにかがやいて、瞬く間に飛び散っていった。
たとえもう二度と会うことがなかったとしても、ふたりの美しい名前と、その日以来焼きついて離れないひとつのイメージを、自分は永遠に忘れることができないだろう。

2020年初頭に広まった世界的な感染症に伴い、巨きな絵を描き終えた頃に考えていた「世界を巡る旅」はいったん延期せざるを得なくなった。それまで続けていた旅のための資金集めも断念して2020年4月には地元の新潟へと戻り、「この先どうするべきか」という問いと独りでひたすら向き合い続けていた。
新潟の実家で過ごす日々は、それまで絵をとおして翼を広げたような気持ちでいた自分にとって、現実という白日の下に何もかも晒されるようで苦しかった。絵との繋がりもどこか遠のいてしまったような気がして、必死でその繋がりを再び追い求めようとしていた。
一方でそれまで制作一辺倒だった生活を省みたい気持ちもあり、新しい土地で一度生活を見直すことを考えはじめた。8月に十勝の大根収穫バイトへ行ったことをきっかけに、半年後には北海道へと引越すことが決まった。
先送りとなった「世界を巡る旅」を念頭に置きながらも、それはまぎれもなく新しい旅のはじまりだった。思えば旅は生きている限りずっと続いていて、自分はただ遠くを歩きたかったのかもしれない。

北海道に移住してからしばらくの間、養護学校で働くことになった。思いがけずそれまでになく収入が安定し、学校の繋がりで3LDK・月約1.3万という条件の公宅を借りられたこともあって、生活をゆっくりと立て直す余裕を持つことができた。レコードプレーヤーを買い、好きな画家の絵を買い、生活に必要な椅子や机を自作したりしながら過ごしていた。
生徒たちと一緒にいた日々はゆったりとしていたようで、先生と呼ばれつつ一緒にふざけあったり、絵のリクエストを幾つも受けて休憩の合間を縫って描いたりしているうちに、あっという間に過ぎていった。けれどそのあいだに自分は、一言ではいい表せない大切な何かをみんなから受けとっていたのだと思う。
彼ら彼女らの生きるすがたは、時として地上の天使そのもののように思われることもあった。けれどそれ以上に胸を打たれたのは、誰もがみな自分と同じ人間であるという事実だった。それまでずっと人間であることに違和感を抱き、どこかで"人間ごっこ"をしながら生きてきたような気持ちでいた自分にとって、彼ら彼女らの存在は不思議なほど温かく、かがやかしく感じられた。いま思えば養護学校で過ごした日々は、"人間であることの入口"に再び立たせてもらうような時間でもあったのかもしれない。
卒業する生徒の似顔絵を一人ひとり描いていた時、かつて「この世で最も美しいのは人間かもしれない」と自分が感じてきた記憶たちが幾つも呼び覚まされた。生徒たちの美しい目を一つひとつ紙に鉛筆で写し取っていくたび、彼ら彼女らとの出会いもまたその一縷なのだと感じた。
存在の祭りに列する人々を描くこと。その彼方にあるものは、かつて巨きな絵を描くときに思い続けてきた"永遠"と、違わず地続きのものなのだと思う。

北海道移住が決まる前の2020年秋、大切な仕事がひとつ形になった。それは音楽家のharuka nakamuraさんとシンガーソングライターのLUCAさんのふたりによって生まれたアルバム「世界」のアートワークだった。そこにはかつて自分が大学生の頃に挫折したはずの「人を主たるモチーフとした絵」が、当時まったく想像していなかった形で自然とあらわれていた。
harukaさんと初めてお会いしたのは、2019年5月のカテリーナの森で行われたSING BIRD CONCERT FINALのことだった。まだ東京であくせくしていた2015年、自分の絵が生まれ変わるうえでの最たる出会いの場となった吉祥寺のOUTBOUNDというお店で、harukaさんの音楽は流れていた。以来その存在をひとつの灯火のように思い続けながら絵を描いてきた自分にとって、harukaさんと出会えたことは巨きな絵がもたらしてくれた、もうひとつの到達点でもあった。
個人的に、アルバム最後の「アシリレラ」という曲が好きだった。アイヌの言葉で「新しい風」を意味し、全曲のなかでもひときわはじまりの予感にみちたそれは、「光から風へ」という言葉を胸に刻んでいた当時の自分をそっと後押ししてくれる、水先案内人のような存在だった。
事実「世界」は北海道に来て以来、ほんとうに多くの繋がりをもたらしてくれた。あたかも絵が自分より先に旅をしていて、然るべき出会いの場を用意してくれていたかのようでもあった。
闇から光へ来たこと、そこで風を感じたこと。それはあくまで進歩というより、それぞれがひとつの状態に過ぎないのかもしれないと思う。燦然とかがやく光の中は、時として永遠そのもののようにおそろしくもあったのだから。
それでもいま自らを象る力となるのは、「自らもまた発光体である」というあざやかな事実でもあるように思う。闇も光も風もすべて自分のなかにあるのだと思えるとき、不思議と安らぎを抱けるのは、そのように生きてこそ人間であり、ひとりの修羅に他ならないからなのかもしれない。
人間であることを希求しながら、人間ならざるものを希求すること。その往還のかなたにあるものを、きっと自分はただ見たいだけなのだろう。

からだは溶けて宇宙となる
宇宙は溶けて音のない声となる
声は溶けていちめんの輝きとなる
そして輝きはかぎりない歓喜の胸に抱かれる
⏤⏤パラマハンサ ヨガナンダ
(真木悠介「気流の鳴る音」より C・サンタナ「Caravansarai」ジャケットから)
北海道に来てからの大切な出会いのひとつに、洞爺湖でtoitaという小さな商店を営む知子さん、そしてそのパートナーであり野生の学舎という名前で活動する祥也さんの存在がある。
最初にtoitaを訪れたとき、ともこさんは当時まだ北海道に来て間もなかった自分の身の上話に、ゆっくりと耳を傾けてくださった。そして「きっと気が合うと思う」と自宅に招いて繋げてくださったしょうやさんは、それ以来洞爺を訪れるたびに真夜中まで話しこむ、大切な友人となった。
しょうやさんもかつては絵を描く日々に明け暮れた人で、今は洞爺湖を拠点にプリミティブな造形の時間(土面づくりや岩絵など)を人々と共に分かち合い、その内に火山のような熱い意志を秘めて、根源への旅を続けている。夜遅くまで話し込んだ次の日の朝はよく湖へ一緒に歩いて行き、凪いで透き通った湖に枝で波紋をつくってみたり、石を零して音楽を奏でたり、さらさらと砂粒を流して光のドローイングを描いたりしていた。

しょうやさんと語りあうたび、「根と翼を共にすること」という言葉がいつも心に思い浮かんだ。生活と制作の両立という道のりは、決してひとりではできないのだということ(孤独でないからこその孤独なのだから)を自明の理としつつ、同時に制作のおそろしさ(その彼方は永遠と繋がっているのだから)をも引き受けたうえで、それを実践する道を探し求めていくことになるのだと思う。その道は一人ひとり、違ったものになっていくのだろう。
今年亡くなった社会学者の泰斗・見田宗介が、かつて真木悠介とペンネームをかえて著した「気流の鳴る音」では、そのためのひとつの道を「全世界をふるさととすること」という言葉で表したあとで、次のように書いている。
われわれの根を存在の中の部分的なもの、局限的なものの中におろそうとするかぎり、根をもつことと翼をもつことは必ずどこかで矛盾する。その局限されたもの⏤⏤共同体や市民社会や人類⏤⏤を超えて魂が飛翔することは、「根こぎ」の孤独と不安とにわれわれをさらすだろうから。…
しかしもしこの存在それ自体という、最もたしかな実在の大地にわれわれが根をおろすならば、根をもつことと翼をもつことは矛盾しない。翼をもってゆくいたるところにまだ見ぬふるさとはあるのだから。
存在それ自体へと至るために、何よりも自分がよるべとしてきたのが描くことだった。はためく鳥の翼でもあるかのようなあの巨きな絵も、未だ一枚の羽根にすぎないものかもしれない。それならばもっと絵を描けばいい。その果てにいかなる決着が待ちうけているにせよ、その翼が然るべきところへと辿り着くまで、どこまでも限りなく。

北海道に暮らしてから自分の作品を描くことはほとんど出来ずにいたものの、かわりに堰を切ったように始まったのが「みんなで一緒に絵を描く」ことだった。それは長らく自分ひとりで向き合ってきたはずの絵をどこまでも押し広げて、時として台風のように烈しく吹きつけてくる「新しい風」だった。
それまで自分が絵でほぼ使うことのなかった派手な色彩が、そこでは全て赦された。ゴールドやピンクや無数の原色たちが飛び交い、過剰なまでの描写は時に紙を引き裂いて、それらを繋ぎ合せることでまた新たな絵を生みだした。描かれたものは尊重され残されることもあれば、あっという間に塗り重ねられて消えてゆくこともあった。
ふだん絵を描くことがない人でも、鉛筆から筆へ、筆から指へと描画する先端が変わっていくなかである種の"解放"が起こり、水を得た魚のごとく絵の具を走らせる、そのような瞬間に立ち会うこともたびたびあった。
時々みんなで描いた絵を思い返しては、それをひとりで描くことを想像するとき、途方もない感覚に包まれた。一体その先に、どんな絵が生まれてくるのだろうか。少しずつ新たな世界が展けていくのを感じる。

みんなで一緒に描くこと、その一連の試みを自分は「OUR songs」というふうに呼んでいた。描くことの起源それ以前におそらく音楽があるということ、そして絵が生まれる前後には、必ず詩(ポエジー)が存在するということ。描くことをとおして繋がりたいのは、描くことそれ自体を超越した先にあるような、ありとあらゆる諸世界との交歓だった。
思えば「世界を巡る旅」で自分が実現してみたかったことのひとつが、まさしくみんなで一緒に絵を描くことだった。気がつくとそれは北海道ですでにはじまり、新しい風景を幾つも見せてくれている。
洞爺湖のしょうやさんと、いつかどこかで、みんなで集まって巨大なひとつの太陽を描こうという話をしたことがある。この地上にさざめくすべてを太陽のおもかげとして、万象の生きて在るさまを、無数のうた、ひとつの讃歌として、描き奏でるように。

世界は雲のように
その形を変えていき
成し遂げられたものはみな
原始へと還っていく
変容と逍遥は
より広く、そして自由に
竪琴を持つ神よ
あなたの永遠の歌が舞い上がる
悲しみを知り尽くすことはなく
愛を学び尽くすこともなく
死によって私たちを遠ざけるものが
明らかにされることは決してない
ただ、大地を貫く歌だけが
救いと祝福をもたらす
それはキース・ジャレットの「Spirits」というアルバムのライナーノーツに引用された、リルケの詩だった。北海道に来て以来くりかえし聴き続けているこのアルバムは、作り手にとっても「音楽の根源」そのものと交歓したかのようなかけがえない日々の中で生み出されたものであり、自分にとってもこれから歩む先10年ほどを予示するかのような、圧倒的な存在感を放っている。
詩を意訳してみた時に流れ込んで来たものは、あまりにもこれからの一切を含んでいるようで、ふるえずにはいられなかった。そこにはこの先描くべき絵の在りようがあり、いつか世界を旅する日々があり、いつかふたたび絶望する瞬間さえもほのめかされているように感じられた。そのことがどこか畏ろしくもあった。
予兆すること、ありとあらゆる徴候に対して鋭敏でいることは、絵を描くうえでなくてはならない感覚なのだと思う。ところがその一方で予兆に頼ろうとするあまり、宿命的なものに囚われてしまうことも、これまでを振り返ると少なからずあったように思う。特にそれは絵の外で、とりわけ誰かと共に生きようとすることにおいて。
完全な自由と完全な宿命が共にあるという、もっとも矛盾した言い方をするとき、不思議とそれこそが本当であるように思われるのはなぜだろう。この世界を、自分の生を、見縊(みくび)ってはならないといつも思う。予兆の外をも信じてみたい自分を、どこかでは赦していたい。真理は決して物事の中心にあるのではなく、世界の果てに誰にも知られることなく、そっと咲きこぼれているものかもしれないのだから。

この三年半のうち最も予期していなかった出来事の一つが、邑里(ゆうり)さんと一緒に暮らすことだった。
かつて自分が絵描きとして駆け出してから少し経った頃に、邑里さんとはインターネットをとおして出会った。巨きな絵の展示で初めて出会って以来、折にふれてそれぞれの近況を話しあいながらお互いが生きていることを有難く思える、大切な存在だった。彼女もまたその道のりのなかで、写真やヨーガとの出会いをとおして、生きることそれ自体が祝福であること、そして自らもまた光を放つ存在であるという思いへと辿り着いた人だった。
邑里さんが自身の活動をはじめるときに「祝(ゆわい)」という言葉と出会い、それを屋号とすることについて打ち明けてくれたとき、無性に嬉しくて仕方がなかった。まるで違う人生なのに、もうひとりの自分を祝福したくなるような、不思議な気持ちに包まれたことを憶えている。
今年のはじめに思いがけず縁が深まり、一緒に生きることを決めてから、瞬く間に半年以上が過ぎた。邑里さんがそれまで長く住んでいた京都を離れて、夏から北海道でふたり暮らしをはじめてからは、お互いにまったく未踏の境地にいる。けれどもう、人間ごっこをしているという感覚はほとんどない。相変わらずおぼつかないことばかりだけど、たしかに自分は人間として生きている。
今年の秋に友人の写真家であるトナカイさんが家に遊びに来てくれて、ふたりの写真を撮ってくれた。
いまここが彼方なのだと、そう思う。

✳︎
この文章も、そろそろ終わりにしようと思う。
「絵の変容を巡る旅」が、巨きな絵の制作と展示を含む2015年夏から2019年春までの4年間を指すならば、そこから来年の春までの4年間は「生活を見つめる日々」に相当することになる。邑里さんと出会ったことで、この4年間もひとつの結実を迎えるように感じている。そしてそこから先は、全く新たな日々が始まることになるのだろう。
冒頭に書いたとおり、来年から自分はふたたび巨きな絵を巡回展示しようと考えている。できることなら、自分が誕生日を迎える5月に北海道で展示をしてみたい。それを船出として南へと少しずつ下っていき、各地で展示しながら最後に生まれ故郷の九州までたどり着くことができたら、そんな構想をしずかに温めている。
最後に巨きな絵を燃やす時がきたら、その時こそ自分も世界へと旅立つのだろう。絵を燃やすことを思いついたのは決していまに始まったことではなく、最初に展示をしたときからぼんやりと頭の中にあった。絵が火となり灰となって空へと還っていく時、その時こそ「はじまりの灯」は光から風へと生まれ変わるのだと思う。
本来なら2020年春にその機会を用意するつもりでいたものの、結局感染症に伴いその話は消えてしまった。結果的にもう一度巨きな絵と共に旅ができるようになったことが、今となっては必然であるようにも思われる。
巨きな絵が燃えるすがたを想像するとき、それはいつも夜のおわりだった。その生が熄(や)むとき、かつて絵の一部が引き裂かれて、その裂け目から思いがけない風景が現れたように、そこにも何かが生まれるのだろうか。いまはまだ全くわからないけれど、この文章で幾度となく引用してみせた真木悠介の、「気流の鳴る音」の結びにある最後の一文にひとつのおもかげを見て、ここでの旅に終わりを告げたいと思う。
「夜明けの光は世界と世界のあいだの裂け目だ。それは未知なるものへの扉だ。」